臨床検査技師が教える「がん検査陽性率」の真実|陽性でもがんとは限らない理由
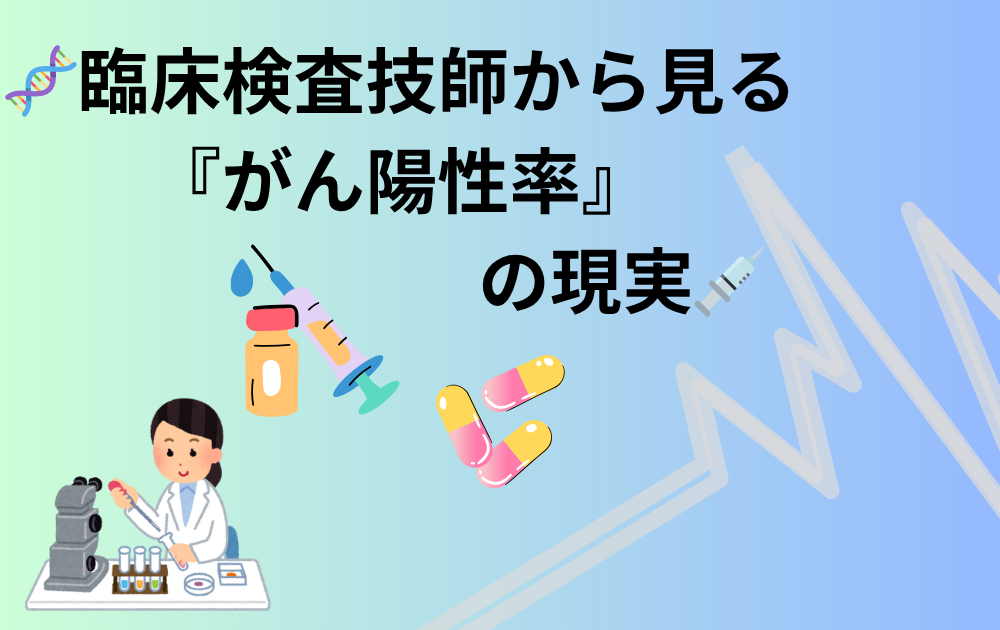
はじめに|「陽性=がん」ではない

健康診断や人間ドックの結果に「要精密検査」「陽性」という文字を見ると、
多くの人が「がんかもしれない」と不安になります。
でも、臨床検査技師としてお伝えしたいのは――
“陽性”=“がん確定”ではないということです。
この記事では、臨床検査技師として実際に多くの検査データを見てきた私が、
「陽性率」の意味・検査の仕組み・結果の受け止め方を、
医学データと臨床現場のリアルからお話しします。
参考:「がん検診と検査の精度(要精検率・陽性反応適中度など)」報告書(厚生労働省)
「陽性率」とは?検査結果の正しい見方
がん検査では、結果を「陽性」「陰性」と2つに分けます。
- 陽性=「がんの可能性がある」状態
- 陰性=「がんの可能性は低い」状態
ここで言う「陽性率」とは、
検査を受けた人のうち、陽性と判定された人の割合のことです。
よくある誤解:「陽性=がん発症」ではない理由
実際には、陽性と出た人の中にも「がんではない」人が多く含まれます。
これは「偽陽性」と呼ばれ、検査の感度が高いほど起こりやすい現象です。
| 判定 | 状況 | 意味 |
|---|---|---|
| 真陽性 | がんがあり、検査も陽性 | 正しい陽性 |
| 偽陽性 | がんがないのに陽性 | 炎症・ホルモン・体質影響など |
| 偽陰性 | がんがあるのに陰性 | ごく早期などで見逃し |
つまり、検査の目的は**「疑いがある人を拾い上げること」**であり、
“診断確定”ではありません。
がん検査の種類と目安陽性率
| 検査名 | 対象部位 | 陽性率の目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 便潜血検査 | 大腸がん | 約3〜6% | 炎症・痔でも陽性になることあり |
| 胃ABC検査(ピロリ+ペプシノゲン) | 胃がん | 約5〜10% | 胃炎でも反応する |
| PSA検査(男性) | 前立腺がん | 約10〜15% | 加齢でも上昇することあり |
| AFP・CEA・CA19-9 | 肝臓・消化器系 | 検査による | 腫瘍マーカー単体では診断不可 |
💡ポイント
- 陽性率は「検査ごとの感度と特異度」で変化します。
- つまり、“陽性が出やすい検査”=“見逃しにくいが誤判定も多い”検査です。
なぜ「陽性=がん確定」ではないのか
臨床現場では、陽性と出た患者さんの多くが再検査で「異常なし」になります。
その理由は次の3つです。
- 炎症やホルモン変動による一時的な反応
- 採血・食事・服薬のタイミングによる誤差
- 体質(貧血・脂質代謝・肝機能)による数値変動
がん検査の結果は、単一の数値だけで判断せず、
画像診断・再検査・経過観察を組み合わせて診断されます。
臨床検査技師として伝えたい「数字との付き合い方」
臨床検査技師として長年データを見ていると、
「数値の変化=病気」ではないケースを何度も経験します。
検査結果を見るときに大切なのは、
「単発ではなく、変化の流れを見ること」です。
- 1回目:やや高め → 2回目:正常 → 3回目:安定
→ こうした推移を見ることで、体調や生活習慣の影響も読み取れます。
女性・働く世代に多い“数値変動”の背景と薬膳的ケア
女性の場合、ホルモン周期によって血液成分や炎症マーカーが変動します。
また、ストレス・冷え・睡眠不足も“偽陽性”の一因となります。
| 不調タイプ | 特徴 | おすすめ食材 |
|---|---|---|
| 冷え・疲れタイプ | 朝がつらい・手足が冷える | なつめ・しょうが・黒ごま |
| ストレスタイプ | 眠れない・イライラ | クコの実・はちみつ・菊花茶 |
| 血行不良タイプ | 顔色が悪い・生理痛 | 黒きくらげ・棗・レーズン |
→ 薬膳の目的は「体を整えて、数値のブレを少なくする」こと。
日常の食事で少しずつ体質を安定させていきましょう。
陽性と出たらどうする?次のステップ
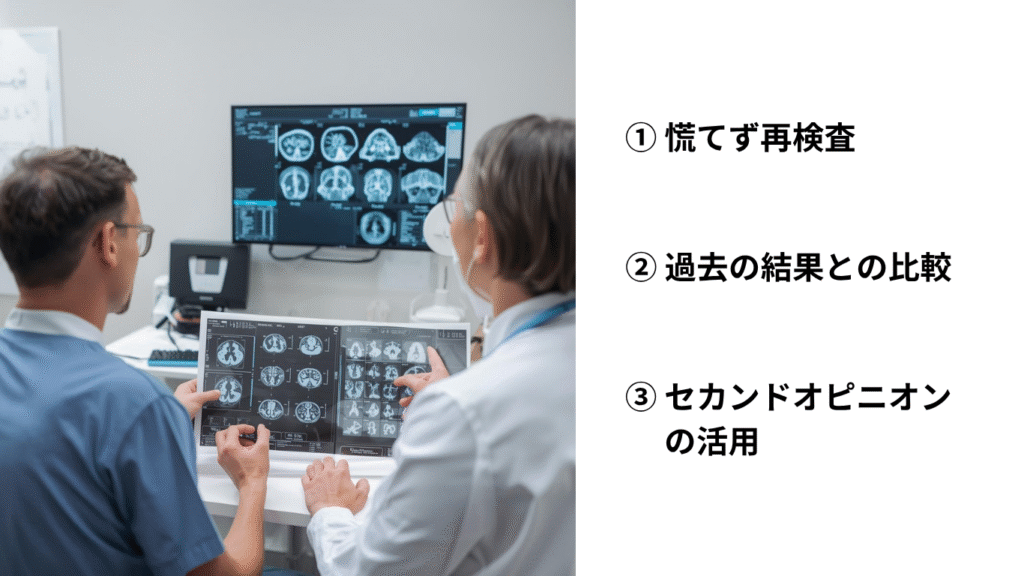
- 慌てず、再検査・画像診断を受ける
→ 1回の検査で全ては判断できません。 - 過去の検査結果と比較する
→ 数値の推移を見ると原因がわかることがあります。 - 専門医(内科・消化器内科など)に相談
→ 必要に応じてCT・MRIなどで精密検査。
💬FAQ:陽性結果を放置するとどうなる?
→ 炎症や良性腫瘍でも数値が上がることがあります。早めの再検査で安心を得ましょう。
まとめ|数値にとらわれず、「体のサイン」として向き合う
がん検査の「陽性率」は、体の状態を映す一つのサインにすぎません。
数字だけに一喜一憂せず、**“今の自分を見直すきっかけ”**として活かすことが大切です。
臨床検査技師としての私の実感は、
「データを正しく理解すれば、不安が知識に変わる」ということ。
もし気になる数値があるときは、
食生活・睡眠・ストレスの見直しから始めてみましょう。
🌿最後に
がん検査の数値は「結果」ではなく「きっかけ」。
正しい知識を持てば、不安は減り、早期発見にもつながります。
臨床検査技師として、
「数字の裏にある体のサイン」を一人でも多くの人に伝えたい——
そんな思いで、この記事を書きました。
※もっと深くがん検査について知りたい人はこちら
書籍:がん検診を信じるな「早期発見・早期治療」ウソ(宝島社)
(一般の方にもわかりやすい内容です)





